英語構文詳解 (駿台受験叢書) 伊藤 和夫(著) 846円
奥が深い伊藤ワールド
この本には構文が凝縮された短い英文に詳細な解説が掲載されていますが、その解説が非常にわかりやすい。短文だから当然でしょ?と思われるかもしれませんが、それは違います。整序問題を通じてなぜそうなるのかがわかりやすく説明されており、吟味しながら読んでいくと奥が深い。まさに英語構文に関するクエスチョンボックス集という感じです。特に印象的だったのは関係代名詞の制限的用法と非制限的用法の解説です。まさに目からウロコが落ちました。一般的な受験参考書ではコンマの有無でしかその違いを説明していませんが、これは違います。英語に限らず言語が持つ行間の意味を教えてくれているのです。私は20数年前の大学受験の際に英文法教室や英文解釈教室を参考にしながら、英文法頻出問題演習や基本英文700選とともにこの本を繰り返して英語を勉強しましたが、その後社会人になってから本棚の整理のためにボロボロになったこれらの本を捨ててしまいました。もし伊藤先生が生きておられたら「意識せずに直読直解ができるようになれば私の役目は終わり。捨ててもらってけっこう」とおっしゃるでしょう。しかし難解な英文でも今では辞書さえあれば正確に読めるようになったのは伊藤先生のおかげ。軽薄短小が好まれ重みのある数々の名著が絶版になっていく今の時代だからこそ永久保存版として再び購入し、お気に入りの小説を読み返すが如く懐かしみながら楽しんで読んでいます。最後に、理論を極めたがために時代から見放され絶版となった「英文法教室」の復刊を強く望みます。
印象に残った本
受験時代に英文解釈教室の基礎固めとして利用しました。当時は「ビジュアル英文解釈」が無かったため、このような目的で利用している人が多かったようです。ただ、「ビジュアル英文解釈」が発売された後は、ずいぶんと評価が下がり、整序問題対策の本と見なされるようになったように思います。しかし、この本は単なる整序問題対策の本ではなく、英語構文の本質を身につける本であり、現在でも、おそらく最も優れているのではと思います。そういった意味で、伊藤和夫師の歩の奈かっでも最も印象に残った本です。ただ、初期に出された本なので、文体が硬く、若干修正すべき部分もありますが、それでも、星20でもいいと考えています。伊藤和夫師が他界されて、今日で10年になりますが、生前にぜひ改訂して欲しかったと思います。
英文法ナビゲータ、構文詳解、ビジュアル英文解釈の順番で。
英文法ナビゲーター、ビジュアル英文解釈の後に一通り読んだのだが、
もうすでに殆どの文法事項が理解できる状態になっていたので
復習する事も無かった。
ただ構文の要点は突いているのでビジュアル英文解釈をやる代わり、
または前に読むのが良いと思う。
ビジュアル英文解釈は接続詞が多く入り組んでいる長文が数多いので
何度も挫折しそうになったのだが、構文詳解は長い文章があまり無いので
分析するのには挫折が少ないと思う。
英文法ナビゲーターの一段階上のレベルだが、構文詳解の説明のしかたは
英文法ナビゲーターに近いので順番にやれば理詰めの説明文により力がつくと思う。
短文を使用した構文の法則性を数多く提示してくれる良書と言える。
その後に演習するビジュアル英文解釈では、一文の中に接続詞などがたくさんある
入り組んだ複雑な長文の中の各名詞節、形容詞節、副詞節、名詞句、形容詞句、副詞句などの、
それぞれの掛かり方と読む順番を演習する段に入る。
構文詳解が文法から構文の橋渡しの本とすれば、ビジュアル英文解釈は構文から長文への橋渡しの本と言える。
英ナビ、構文詳解、ビジュアルの順番でやるのがスムーズに行くと思うのでお勧めします。
難しい上に古くさい
現在容易に入手できる「伊藤本」では最も古い物でしょうが、
30年間一度も改訂されていないが故の古くささ、
内容の難解さと相俟って「使えなさ」も最高でしょう。
この後に出た「教室」3部作、ビジュアル英文解釈、
新・英頻、英語総合問題演習、英ナビ・・・と辿っていけば
「著者の目指していたもの」は分かりますし、
その意図も「学習法」や「解釈教室」などの前書きを見れば
はっきりするでしょう。
「生徒に英文の構造の全体像を示すこと」に躍起で
「生徒の顔が見えていなかった」時代の伊藤氏を知る
「骨董的価値」のある本ではありますけど、
「受験参考書」としての存在理由はもはやないし
今後評価されることもないでしょう。
準英作文参考書
伊藤英語の構文・英作文の参考書兼問題集。基礎レベルの方(初学者なら辞書を使いながら)でも整序問題を通じて主語、目的語、補語、動詞句、助動詞、仮定法、名詞節、itの構文、関係詞、準動詞、副詞節、否定、比較等を根本から無理なく学べる。薄めの一冊に例題、練習問題が豊富な上に解説も詳しく丁寧。著者こだわりのマニアックな索引もついているので自分の知りたいことを索引から探して学習することもできる。但し、いわゆる読解や文法の参考書ではない。同著者が書いた構文の書なので重なるところもあるが、「英文解釈教室」(研究社)が読解のための構文の学習書なら本書は英作文のための構文の学習書といったところである。書評ではないが、他のレビュアーの方々が話題にしているので一言、本書の「not 比較級」と「no 比較級」の違いの話はとても解りやすいが、3人の在米アメリカ人に聞いたところ、no more thanにはsame asとless thanの両方の意味があるそうです。英作文ではわざわざ廃れた否定形を用いず、same as 〜 or lessとかat mostを使った方が意味明瞭でいいと思う。最後に著者は英文解釈や文法で定評・批判があるが、TBS東大入試速報での英作文の解説はとても良かった。駿台生の頃、英作文の勉強の仕方を聞いたら「一冊、書かなければならないけれどそんな気力ないねー」とあっさり断られてしまいました。と言う訳で、本書が著者唯一の準英作文参考書といったところでしょうか。因みに本書に出てくる英文と「基本英文700選」(同著者・駿台文庫)の例文、結構重複しているので、本書をやってからだと700選も覚えやすいのでは。
英文和訳演習 (基礎篇) (駿台受験シリーズ) 伊藤 和夫(著) 632円

英語学習に和訳は不要
英文和訳の方法を長々と説明しているが、そもそも和訳とは英語と日本語の双方を理解してこそできることである。通訳家や翻訳家になるための訓練としてならともかく、英語の理解が覚束ない高校生のすることではない。英文和訳が大学入試の主流であるのは事実であるが、だからといって和訳が正しい学習方法というわけではない。
英語学習の道標
巷間では『多読、多読』と高校受験対策の頃からいわれ、根本的に自分の学習法で「何が悪かったのか?」がわからなかった方。ぜひこの本から始めてみてください。
この本は伊藤先生が毎回作っていた「駿台模試」や駿台の「校内テスト」で使われた問題を中心に編まれたもので、この基礎編は高1レベルから高2レベルの問題を扱っています。問題が1ページ以内のごく短く、大学受験生には平易に感じられるかもしれません。それに対し解説が5ページくらいさかれています。そして(少なくとも伊藤先生がいたころは)英文和訳の採点がどのような基準でなされていたのかを知ることができると思います。そしておそらくその基準は大学の採点基準を上回る厳格さであることは、間違いないと思われます。
しかし、この本を平易に感じられなければ、自分の基礎が甘かったのだと思って、『ビジュアル英文解釈PART1』(駿台文庫)をやるなどして、基礎を固める必要があると思います。
ところでぼくの評価がなぜ星4つなのか。それはこの本による直接的な効果、即効性に乏しいのではないか、という懸念があるからです。これをやったからといって力が付いた、という性質の本ではありません。ですから、高3の春くらいに一気にやってしまって、その後のプランを立てるための道標、地図のようなものとしてやることをおすすめします。
やってみて!
浪人時代にひととおり英語の勉強をすませ、もう一度基礎的な参考書を何かやってみようかなと思ってやりました。僕自身英語がかなり得意になったしそんなに間違えないだろうと思っていたのですがかなりケアレスミスが目立ちました。私大を目指す人は英文を速く読むことに専念し基礎的な英文を訳したりする機会が少ないと思うのですが、もし今一つ英語の成績が上がらないとしたらやってみたらどうでしょうか?上級編までやる必要はないと思いますが中級までしっかりとこなすと早稲田や慶応などの難関大もそれほど怖くなくなってくると思います。英文の速読とは英文の精読の上にあることを忘れないでください。
英文解釈教室 入門編―高1レベルからラクラク学べる 伊藤 和夫(著) 1229円
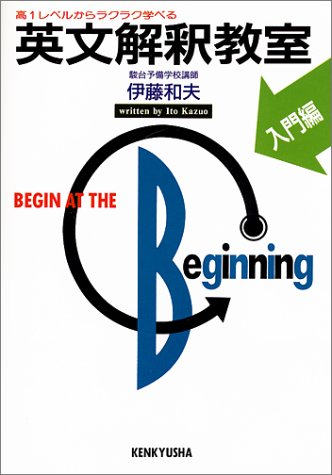
生徒に渡す一冊。
家庭教師で教えていた生徒が、中学を卒業するときに手渡す一冊です。中学卒業時では、若干難しい単語熟語を含みますが、それなどには左右されない意義ある内容が詰まっています。
要は「何を軸にして英語を読むか」です。
高校以上の英語では、動詞・名詞・関係詞などの品詞や、構文的な文法を通り一遍等にやります。でも、高校の内容を教えるのに精一杯の人間たちでは、「なぜ品詞や、構文が重要か」を伝えられない人がほとんどだと思います。それに対する確かな答えが、このシリーズには書かれています。
文体や書式が古びることがあっても、内容の価値はなんら薄れていくことのない一冊であり、シリーズだと思います。
構造から読む。
英文解釈教室シリーズ3冊の中の1冊目。
スタート地点はビジュアルよりもカンタンなところから。
名詞とか形容詞とかそんなレベルからのスタート。
本当の意味での基本からのスタート。
ビジュアルがある程度の文法知識を必要する一方で、
この本はそんなカンタンなレベルからのスタートだから
ビジュアルよりはとっつきやすいハズ。
これを読めば基本的な文法まで理解できるというおまけつき。
英語初心者レベルの人は読むべし。
ただ、著者の堅くて理屈っぽい解説が万人受けするとは思えないのも事実。
でも、フィーリングで、感覚で、なんとなく内容がわかれば良い、
っていうようななんていう風潮にだまされている人にはぜひ目覚めて欲しい。
本物の英語など必要ないという輩に最適
私は伊藤和夫の一連の著作をまったく評価していない。なぜならそれらのすべてが「和訳を通して生徒の理解力を判定できる」という誤った考えに基づいて書かれているからである。(実際にある著書の中でこのことを明言している。)勘違いしている人が多いのではっきりと言っておくが、入試という点取りゲームのルールは正しい英語のそれからずれている。本物の英語を習得したい方は正しい教材を用いて学習しよう。「本物の英語」や「生きた英語」などクソ食らえという輩には本書のような受験英語モノが最適である。
受験生はこれやれ!
自分は英語が苦手で大学に行くの諦めてた。教師が薦めるものや友達が使ってる参考書を観ても、読んでるだけじゃ集中力続かくてわからなくなっちまうといったような、頭良い悪い以前のレベルだったから、最初に小問やって、それにリンクしてる文章に行く様な流れがないと飽きちゃうのでそんなムシノイイ本がないかと探してた。
周りは、ビジュアルやってて、それで、伊藤先生を知って、ビジュアルみたけど、読むだけの構成じゃんよ。で、伊藤本で小問→文章の流れがあって高1レベルから始められる本て事で、本書始めた。
でも、集中力ないし、勉強してなかったから最初は伊藤先生の説明わからなくてね。
で、もっと簡単な事からって事で、
薬袋善郎先生の、『基本からわかる 英語リーディング教本』をやり始めた。
そしたら、集中できて、始めて、エロ本以外の本を通読できたよ!そしたら英語を好きになって集中力がついたのかな。
で、また本書やり始めたら、伊藤先生がたくさんの人から尊敬されてるのがわかった気になって、調子づいて
入門→基礎→本編
て流れで勉強すすめたら英語できる様になったよ!
最近、高校生で基本から勉強する人が増えてるみたいだけど、注意したいことがある!
物事をちゃんと基本からやるのと、簡素な説明で基本ぽくやるのとを勘違いすんな!最近じゃこの事を受験生が勘違いするような講義系の参考書が増えてるけど、問題は中身だよ!
数学では藤田宏先生がいい!黒大数の著者だぞ!読むのかったるい奴は『理解しやすい』か『これでわかる!』やってから黒大数いけ!
話しを戻すと、伊藤和夫先生と薬袋善郎先生は確かに言葉難しいよ。だけど、基本からやってくれてるよ。
伊藤が取っ付きにくかったら、薬袋やってから伊藤いけや!
何で☆四つなのかは、薬袋からやらないと理解できない馬鹿な人間もいるから。
本編終われば受験英語卒業
(TωT)/
超正統派英文解釈参考書
「高1レベルから学べる(楽ではないと思う)」との謳い文句通り、
文型より更にその前の段階の「この単語は名詞か動詞か」という演習から導入されています。
世に「基礎」や「入門」と謳っている本は数あれど、
本当の意味での「基礎(このシリーズには基礎編もありますが)」というものを
語っているのはこの本だけではないかとさえ思います。
「文法」や「構文」の基礎を全て示しているわけではありませんが、
少なくとも「基礎を固めたい」という人に対する正解の一つが
この本ではないでしょうか。
難点は、地道にコツコツやるタイプの人には最適ですが
「気が付いたら最後までやっていた」という内容ではないので
忍耐が必要な点でしょうが。
新・英文法頻出問題演習 (Part2) (駿台受験シリーズ) 伊藤 和夫(著) 819円

頻出問題の羅列
Part1 と同様に入試頻出問題の羅列に終始している上に、解説も簡略され過ぎている。入試のためだけに英語を学んでいる人にはこれで十分なのだろが、深く理解したい人はこれではまったく足りない。本書のようなものを使っていたのでは、仮定法ではなぜ「事実に反する仮定」に通常の条件節if+現在形ではなく過去形を用いるのか、まるで理解できない。本書は入試対策の定番だが、まともな英語学習に役立つか否かという点から見ればまったく評価できない。
前置詞の感覚がつかめる本
本書は、大学受験英語の熟語問題対策として有効であることがよく知られているが、さらに重要な点として、前置詞の使い方に関する感覚がつかめることがあげられる。前置詞については、基本的意味、空間的感覚を知った後では、問題演習を反復して血肉化することが必要である。このためには、日本語からの類推だけではカバーし切れない用法を含めて、特に覚えて、慣れない限り使いこなせない用法を網羅した本書を繰り返し学習することが有効であり、大学受験生だけでなく社会人にも薦める。
英語苦手人間のための 『英頻』 扉の開き方
こういう問題集は語彙や文法が弱い方は、最初の取っ掛かりが大変です。本書の扉の開き方ですが、初めは問題文中の未知熟語などを辞書や文法書で調べて取り組みましょう。これは先生自身が薦める方法です。「学力の足りない初心者は、問題を解く際には辞書などを参照すればよい。問題自体を取り組まないよりマシ」です。「辞書を使ったら全部答えられるじゃないか」と言われるかもしれませんが、試して見て下さい。力が足りない人はそれでも正答するのは至難の技なのです。何度も転んで自転車に乗れるようになるように「間違って当たり前」の気持ちで(辞書や文法書の助けで)壁を越えましょう。もしこの『英頻』が難しすぎると感じたら同じ伊藤先生の『英文法のナビゲーター』の使用をお勧めします。『英ナビ』は『英頻』の弟分的存在で構成も同じで、解説もこちらの方が詳しいですから『英ナビ』を終わらせてから『英頻』に戻るというのが得策だと思います。
ただ丸暗記の熟語問題集ではありません
以前から好評の同書が2分冊になり、その熟語編です。indexを見ればわかるようにこのそう厚くない1冊に大切な熟語が網羅されています。分冊の文法編の参照指示も多く、2冊合わせて勉強するとより力がつくことでしょう。また同書内の参照箇所も明示されており、面倒くさがらず必ずそこを学習すべきです。熟語の力を問題演習を通して増強する格好の参考書です。もちろん例文には日本語付きですから、力の余った人は例文丸暗記など使い方いろいろのお薦め熟語演習書です。
英語総合問題演習 基礎篇 伊藤 和夫(著) 1050円
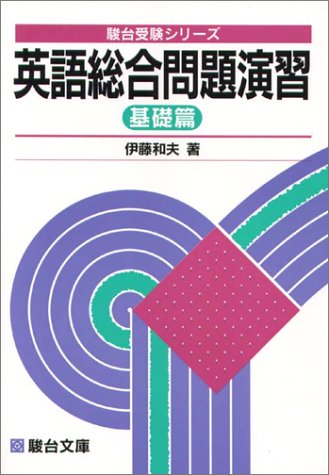
真の総合問題とは
穴埋め、英文和訳、代名詞の内容を書かせる問題などなど、こういう的外れなものを総合問題だと思っている人はTOEICやTOEFLの問題と比較してみるといい。総合的な英語運用能力を測るための問題とはどのようなものなのかよく理解できるであろう。受験英語の様々な形式はすべて受験者の目先を変えるためのものであり、その能力を測るためのものではない。総合的な実力を養成したければ、学習者のどのような能力を測るのか、明確に意図して作られた問題を解くべきである。
あなたの英語力をおさらいしよう。
大学入試のために書かれた本だが、大人が英語をおさらいする時に必須のアイテムといえる。
大学入試にでてくる問題パターンを網羅している。入門から上級まで自分のレベルに合わせて、いざトライ。上級まで修了したら一通りの英語力が確認できたと言えるでしょう。伊藤先生の名著です。
